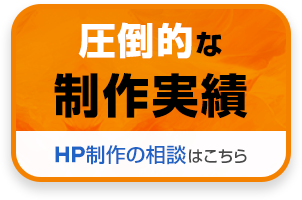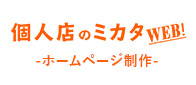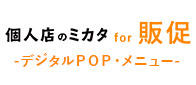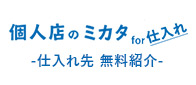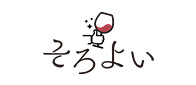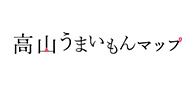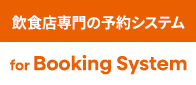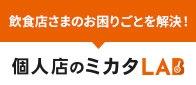はじめに

飲食店の火災保険は、飲食店を新たに出店&開業する方にとってはとても重要な保険です。
一般的な住居の火災保険とは異なる点が数多くありますので、本記事をぜひご一読ください。
今すぐ自店舗にあったおすすめの安い保険を教えてほしい、という方は、以下のボタンよりお問い合わせください。
担当コンサルタントが飲食店様の立地、規模、構造、業種業態などを加味した上で最適な保険内容をご紹介させていただきます。
こちらのボタンよりご依頼ください。
どうぞお気軽にお問い合わせください。 よろしくお願いいたします。
目次
【1分でわかる】この記事の結論:飲食店の保険選び
(火災・水漏れ・食中毒などをカバーする店舗用の火災保険)
※店舗の規模や構造、補償範囲によって変動します。
\あなたの店舗に最適な保険を無料診断/
飲食店と一般的な火災保険の違い

それでは具体的に飲食店の火災保険と一般的な住居の火災保険は何が違うのでしょうか。
補償対象のもの
店舗の建物や火を取り扱うガスコンロやフライヤーはもちろん、業務用冷蔵庫や食器洗浄機などの厨房機器、備品など飲食店を運営する業務に必要な設備が対象になります。
上記の通り、火災保険と聞いてイメージするのは、「火災に対する保険が対象」だと考えられますが、飲食店の火災保障の範囲は少し違います。保障の範囲が広く設定されているのです。
例えば、落雷が火災の原因になった場合も保障対象となっています。それ以外でも台風や突風、竜巻などの風災や、大雨や台風による水害、直径5mm以上の氷の粒である雹による被害の雹災など、火災ではありませんが補償対象となります。
また、水害については、浸水の高さによっては十分な補償が受けられない場合があるため、要件の確認が必要です。高さ要件がなく保険金額を受け取る保険も検討しましょう。
1. 火災による損害
最も基本的な補償です。以下のような様々な原因による火災損害が対象となります。
調理中の失火:
ガスコンロの火の消し忘れ、フライヤーの油からの発火など、飲食店で最も起こりやすい火災原因の一つです。
漏電・電気設備のショート:
古くなった配線や厨房機器の電気系統の不具合、タコ足配線などによるショートが原因となる火災です。
特に多くの電気厨房機器を使用する飲食店では注意が必要です。
放火・もらい火(近隣からの延焼):
残念ながら、第三者による放火や、隣接する建物からの延焼によって被害を受ける可能性もゼロではありません。
こうした場合の損害も補償されます。
その他:
落雷が火災の原因になった場合も補償対象です。
また、ガス漏れによる爆発・火災なども対象となります。
これらの火災によって、店舗の建物本体のほか、ガスコンロやフライヤー、業務用冷蔵庫、食器洗浄機といった厨房機器、客席のテーブルや椅子などの什器備品、冷蔵庫内の食材や在庫商品など、飲食店を運営する業務に必要な設備や物品が燃えたり、消火活動によって水浸しになったりした場合の損害が補償されます。
2. 自然災害による損害
近年、その威力を増している自然災害による損害も、火災保険の重要な補償対象です。
風災・雹(ひょう)災・雪災:
台風や竜巻、暴風による屋根や窓ガラスの破損、看板の落下。
直径5mm以上の氷の粒である雹(ひょう)による窓ガラスや外壁の損傷。
大雪による建物の倒壊や屋根の損壊、雪の重みによる雨どいの破損など。
特に、テラス席のある店舗や、大きな看板を設置している店舗などは注意が必要です。
水災:
近年多発するリスクへの備え: 大雨や台風、集中豪雨、ゲリラ豪雨による洪水、河川の氾濫、土砂崩れ、高潮などによる浸水被害を補償します。
地域特性に応じた重要性:
店舗が河川の近く、海沿い、低地、過去に浸水被害があった地域などに立地している場合は、特に水災補償の必要性が高まります。
ハザードマップなどで自店舗のリスクを確認しておくことが重要です。
具体的な被害例と注意点:
<床上浸水による厨房機器の故障や汚損、食材や什器備品の廃棄、内装の復旧費用などが対象となります。
ただし、水害については、契約内容によって浸水の高さ(例:床上浸水以上など)によっては十分な補償が受けられない場合があるため、ご自身の契約における支払い要件の確認が非常に重要です。
場合によっては、高さ要件がなく保険金額を受け取れる保険も検討してみましょう。
3. その他の事故による損害(保険契約によって異なります)
上記以外にも、契約内容によっては以下のような事故による損害も補償対象となる場合があります。
水濡れ(みずぬれ):
給排水設備の事故(水道管の破裂など)や、他人の戸室で生じた水漏れによる損害。
盗難:
店舗への侵入による什器備品や商品の盗難、それに伴う窓ガラスやドアの破損。
破損・汚損(はそん・おそん):
予期せぬ突発的な事故(例:自動車の飛び込み、物の落下・飛来)による建物や什器の損壊。
休業損害:
火災や自然災害などで店舗が休業せざるを得なくなった場合の、復旧までの間の売上減少や家賃・人件費などの固定費(別途特約が必要な場合が多いです)。
ご自身の店舗がどのような保険に加入しており、どこまでの範囲が補償対象となっているかを正確に把握しておくことが非常に大切です。
保険証券や契約のしおりを確認し、不明な点は保険会社や代理店に問い合わせましょう。
補償対象外のもの
上記の通り、飲食店の火災保険は一般的な住居に比べて落雷、風災、雹災などにも対応するように広く設定してありますが、補償対象外になるものとして意外なのが「地震」です。
地震が原因で火災が発生する、というニュースを年に数回は目にしますがこのようなケースは火災保険の対象にはならず、地震保険の補償対象になります。
特約という形で別途契約をする必要がありますので、地震原因の火災に備えたい方は申込みを忘れないようにしましょう。
飲食店に火災保険が必要な理由

もしも自社経営店舗で火災が発生した場合、店舗の修繕費用や設備の再購入、休業中の損失など、その損失額を支払うのは原則として自社・自己負担になります。
営業時間前の仕込み中のボヤ騒ぎ程度でしたら損失は大きくありませんが、万が一、営業中に火災が発生した場合、その被害は計り知れません。
飲食店では、調理中の火の取り扱いはもちろんのこと、厨房設備の老朽化や過負荷による電気設備のショートなど、様々な火災リスクが潜んでいます。
ひとたび火災が発生すれば、店舗の設備や商品が焼失するだけでなく、来店されたお客様の安全に関わる事態となり、近隣店舗も営業ができなくなる可能性も出てきます。
さらに、自店舗が火災の原因ではなく近隣店舗のもらい火で火災になり営業ができなくなる可能性も十分に考えられます。
これらの損失額を自己負担で賄うことができれば当然火災保険に加入する必要はありません。
しかし、火災による損害は建物や設備だけに留まらず、休業期間中の収益減少、従業員の給与、そして場合によっては近隣への賠償責任まで発生する可能性があります。
このように損害に限度がない以上、全ての費用を自己資金でカバーするのは現実的な話ではありませんし、事業の再建は困難を極めると考えられます。
経済的な基盤が揺らげば、大切な従業員や取引先を守ることも難しくなってしまうでしょう。
加えて、火災を起こしてしまった場合や、被害からの復旧に時間がかかってしまうと、顧客からの信頼を失い、いわゆる社会的信用が低下するリスクも無視できません。
一度失った信用を取り戻すのは容易なことではありません。
だからこそ、これらの多様なリスクから大切な事業を守り、万が一の際にも経済的なダメージを最小限に抑え、迅速な事業再開を目指し、
そしてお客様や社会からの信用を維持するためにも、火災保険は必ず加入すべき保険と言えるでしょう。
それは、未来への投資であり、安心して経営を続けるための重要なセーフティネットなのです。
火災保険の保険料相場

飲食店が加入する火災保険の保険料は、様々な要因によって変動します。
特に飲食店は火を扱う機会が多く、一般的なオフィスや小売店に比べてリスクが高いため、保険料も高くなりやすい傾向にあります。
この記事では火災保険の保険料の決まり方と、コストを抑えるための方法について紹介します。
火災保険の保険料はどう決まる?
火災保険の保険料は、以下のような要因によって決まります。
1. 建物の所在地
・商業地・繁華街:隣接する店舗が多く、火災が広がりやすいため、保険料は高め。
・住宅街:比較的火災リスクが低く、保険料も抑えられる傾向。
・郊外エリア:消防署までの距離が遠いと、火災の際の消火対応が遅れるため、保険料が高くなる場合がある。
2. 建物の構造(耐火・非耐火)
・耐火建築物(鉄筋コンクリート造など):火災が発生しても燃え広がりにくいため、保険料は低め。
・木造建築物:火が燃え広がりやすいため、保険料が高くなりやすい。
3. 建物の面積や階数
・広い店舗や複数階の飲食店は、被害が大きくなりやすいため保険料が高くなる傾向。
・小規模なテイクアウト専門店などは、比較的保険料が安くなる場合がある。
4. 業態(居酒屋・カフェ・焼肉店など)
業態によっても火災のリスクが異なり、保険料に影響します。
・焼肉店・鉄板焼き・ラーメン店:火を多く使うため、火災リスクが高く、保険料も高め。
・カフェ・喫茶店:ガスコンロの使用が少なく、火災リスクが比較的低いため、保険料は安め。
・ファストフード・デリバリー専門店:火の使用量が少ない場合、保険料が抑えられることが多い。
5. 補償内容(補償額・特約の有無)
・高額な補償を設定すればするほど、当然ながら保険料も高くなる。
・特約(例:水害補償、休業補償、盗難補償など)を付けると、その分保険料が上がる。
火災保険を安く抑えるコツ
火災保険は、工夫次第でコストを抑えることが可能です。
以下のポイントを押さえ、必要な補償を確保しながら保険料を節約しましょう。
1. 免責金額を上げる
免責金額(自己負担額)を設定することで、保険料を下げることができます。
例えば、「火災時に10万円までは自己負担する」という条件を付ければ、保険料が割安になります。
2. 不要な特約を外す
保険にはさまざまな特約がありますが、すべて付けると保険料が高くなります。
・必要な特約だけを選ぶ(例:火災補償は必要だが、水害補償は不要など)
・すでに他の保険でカバーできる特約は外す(例:店舗の家財補償は別の保険でカバーしている)
3. 耐火設備の導入で割引を受ける
耐火扉、スプリンクラー、消火器の設置など、防火対策を強化することで、保険会社によっては保険料の割引を受けられることがあります。
4. まとめて契約する
火災保険だけでなく、賠償責任保険や休業補償保険なども一括で契約することで、割引が適用されるケースがあります。
(一般的な)店舗総合保険について

飲食店経営には、火災以外にも様々なリスクが潜んでいます。
今まで見てきた通り、火災保険で様々なリスクに備えることができますが、火災保険だけではカバーできないリスクも飲食店には多いため、
火災保険と合わせて店舗総合保険の加入も検討しましょう。
飲食店の店舗総合保険とは、その名の通り、店舗運営に関わる多様なリスクに総合的に備えるための保険です。
具体的には、上述の通り「火災」はもちろん、「落雷」「風災」「雹災」「雪災」などの自然災害、さらには日常業務の中で起こりうる「水濡れ(給排水設備の故障など)」「盗難」「偶発的な事故による破損・汚損」といった店舗の物理的な損害、そして業務中の事故など、飲食店営業で想定されるリスクに対し総合的な補償を提供します。
加えて、火災や自然災害などで営業が困難になった場合の「休業損失」を補償する機能も重要な柱です。
特にテナントとして飲食店を経営する場合、店舗総合保険では、ご自身で費用をかけた内装や厨房設備、什器備品といった財産を守る補償に加え、万が一、火災や水漏れなどで大家さん(貸主)の建物に損害を与えてしまった場合に備える「借家人賠償責任保険」も非常に重要になります。
これは店舗総合保険の特約として付帯できることが一般的です。
個人事業主におすすめの保険
店舗総合保険は個人事業主に人気の保険です。
なぜなら、一つの保険で火災はもちろん、ガス漏れ・水漏れや盗難などの物理的な損害までカバーし、さらに火災による営業停止により営業ができない場合の補償なども提供されるため、事業と生活が密接に結びついている個人事業主の経営基盤を多角的に守ることができるからです。
特にテナントで飲食店を経営する個人事業主の方は、以下の点を重視して店舗総合保険を検討しましょう。
1.自己所有財産の補償:
ご自身で投資した内装、造作、厨房設備、什器備品、在庫商品などが、火災、自然災害、水濡れ、盗難などで損害を受けた場合に、しっかりと再調達または修理できる保険金額を設定することが重要です。
2.借家人賠償責任保険の付帯:
大家さんに対する法律上の損害賠償責任(例:火災で借りている物件を損傷させた場合)をカバーします。
賃貸借契約で加入が義務付けられていることも多いため、契約内容を確認し、必要な補償額を確保しましょう。
3.休業損失の補償:
店舗が損害を受け休業した場合の粗利益や固定費を補償します。
個人事業主にとっては収入が途絶えることが経営の死活問題に繋がるため、復旧までの期間を考慮して適切な補償額・期間を設定することが肝心です。
店舗総合保険と企業総合保険との違い
店舗総合保険と似たものに「企業総合保険」がありますが、補償範囲や対象となる企業規模に違いがあります。
店舗総合保険:
主に店舗の建物(自己所有の場合)や設備・什器・商品といった「モノ」の損害、休業損失、そして店舗運営に関連する賠償責任(借家人賠償責任、施設賠償責任など)をカバーします。
比較的、飲食店のような店舗ビジネスに特化し、必要な補償を選びやすい構成になっています。
個人事業主や中小規模の飲食店に適していることが多い保険です。
企業総合保険:
店舗のリスクに対する補償はもちろん、それらに加えて従業員の業務中の事故に対する補償(使用者賠償責任など、労災保険の上乗せ部分)、店舗スタッフの事故などの労災(※法定の労災保険とは別に企業が任意で加入する部分)、製造物責任(PL保険)、情報漏洩リスク、取引先を含めて起こった問題に関する賠償責任などリスク全般を補償します。
つまり、店舗総合保険は飲食店に特化していますが、企業総合保険は飲食店に限らず企業運営全体をカバーする万能型の保険です。
そのため、より大規模な企業や、複数の事業を展開している企業、海外取引がある企業など、広範で複雑なリスクに対応する必要がある場合に適しています。
飲食店の個人事業主や小規模な店舗であれば、まずは店舗総合保険で自店に必要な補償を過不足なく確保することが基本となります。
店舗総合保険の保険料相場
では実際店舗総合保険に加入するのにいくらするのか、気になりますよね。
一般的には月額4000円〜、年5万円~20万円程度です。
費用の相場は、店舗の所在地、規模、構造、業種業態によって異なります。
前述の通り、火災保険は「落雷」「風災」「雹災」によっても異なりますので例えば台風が多い地域、積雪が多い地域などはリスクが高まりその分費用が高くなる可能性があります。
また、どこまでカバーするかによっても費用は異なります。
特に営業損失補償額は任意の金額で設定可能ですのでそれにより保険料は増える可能性は当然ありえます。
飲食店の保険に関するよくある質問
飲食店経営における保険の必要性は理解していても、具体的な内容や選び方については疑問も多いことでしょう。
ここでは、飲食店の保険に関するよくあるご質問とその回答をまとめました。
飲食店を開業する方は火災保険と店舗総合保険でリスクに備えましょう!

今回の記事では、「飲食店の火災保険」そして「店舗総合保険」を中心に、飲食店経営を取り巻く様々なリスクと、それらに備えるための保険の重要性について内容をまとめました。
上述の通り、飲食店の「火災保険」や店舗総合保険は、火災だけでなく自然災害や日常の事故、休業損失など、一般的な保険と比べても適用範囲が広い保険になります。
それは即ち、店舗営業には様々なリスクが起こり得ることの裏返しでもあります。
飲食店開業を目指し、夢や希望に膨らむタイミングに「火災」などのリスクに目を向けることは、もしかしたら難しいタイミングかと思います。
しかし、万が一の事態はいつ起こるかわかりません。
安心して事業を継続し、お客様に愛され、長く愛されるお店作りのためには、不測の事態から大切な店舗と経営を守る「保険」はとても重要になります。
火災保険や店舗総合保険は、補償内容が多岐にわたり、またテナント契約の状況や店舗の特性によって最適なプランも異なります。
「自分の店にはどんな補償が必要なんだろう?」「保険料は適正かな?」といった疑問は当然のことでしょう。
そこで重要なのが、保険の専門家への相談です。
飲食店の保険について誰に相談していいかわからない、自店舗にあった保険を選びたい、できる限りコストを抑えたいという方は保険のプロにご相談ください。
保険の専門家が飲食店様の立地、規模、構造、業種業態などを加味した上で最適な保険内容をご紹介させていただきます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。 よろしくお願いいたします。